はじめに
こんにちは、みなみです。
私はこれまで工場勤務から飲食、そして営業職へと3度の転職を経験してきました。
その中で一番役に立ったのは、実は求人サイトではなく社会保障制度でした。
転職はキャリアアップのチャンス。しかし収入が一時的に途切れるなど、生活の不安も大きいですよね。
そこで今回は、私が実際に活用した制度を含め、転職前後に知っておくべき5つの社会保障制度を紹介します。
つまり、この記事を読めば「知らなくて損した…」を防げます。
⬇️私の過去の経験談は他にも⬇️
1. 失業保険(雇用保険)【私のリアル体験】
制度の概要
失業保険は、働く意思があるのに職を失った人へ支給される給付金。
離職後7日間の待期期間+1週間の給付制限後、失業手当を受給できます。
失業保険の詳しい情報についてはこちら👈
私の体験談
飲食店を退職した際、次の職が決まるまで約3か月。
しかしハローワークで申請し、月12万円前後の手当を受給。
おかげで焦らず、自分に合う会社探しに集中できました。
金銭面は結構心のゆとりになったのが正直大きかったです。
ポイント
- 退職時に離職票を必ず受け取る
- 7日間の待期期間を考え、早めにハローワークへ
- 求職活動実績(面接やセミナー参加)を2回以上提出
つまり、失業保険は転職を安心して進めるための強力な味方です。
2. 国民健康保険・健康保険の任意継続
退職後は、健康保険の切り替えが必要になります。
そのため退職日の翌日から14日以内に市区町村で国民健康保険に加入するか、
前職の保険を最長2年間任意継続するか選びます。
ここが重要
- 前職の保険証は返却必須
- 所得に応じて保険料が変動
- 任意継続の方が保険料が安くなる場合もある
一方で手続きを怠ると医療費が全額自己負担になるので注意してください。
そこで退職前に保険料のシミュレーションを行い、どちらが得か比較しましょう。
3. 国民年金&免除・猶予制度
退職すると厚生年金から国民年金に切り替わります。
しかし無収入の期間があると、保険料が負担に感じることも。
そこで便利なのが「免除・猶予制度」です。
- 全額免除・半額免除
- 学生納付特例(若い世代向け)
さらに免除申請をしておけば、将来の年金受給資格を守れます。
つまり、支払いが厳しい時期でも安心して次の職探しができます。
4. 住民税・所得税の支払いスケジュール
住民税や所得税は前年の所得に応じて課税されるため、退職後にまとめて請求が来ることも。
私も初めての転職時に予想外の金額が届き、一瞬ひやりとしました。
対策
- 退職前に源泉徴収票を必ず受け取る
- 住民税は口座振替にして延滞を防止
結果的に準備していたおかげで、思わぬ出費にも落ち着いて対応できました。
5. 職業訓練(ハロートレーニング)
さらにスキルアップを目指すなら職業訓練は見逃せません。
失業保険を受けながら無料または低額でスキルを習得できます。
メリット
- 受講中も失業手当が延長支給
- プログラミング、簿記、介護など多彩なコース
私の友人はこの制度でWebデザインを学び、結果的に希望する企業へスムーズに転職。
つまり空白期間をスキルアップ期間に変えられるのです。
転職前にやっておくべき4つの準備
- 生活防衛資金の確保
3〜6か月分の生活費を目安に貯金。 - 必要書類のリスト化
離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証など。 - 窓口情報の事前確認
ハローワークや市区町村の休日・必要書類を把握。 - 副収入・資格プラン
職業訓練やオンライン講座など、空白期間を学びの時間に。
制度を使って感じた安心感
失業保険を受けたことで、
- 焦らず自分に合う企業を探せた
- 面接準備に時間を使えた
- メンタル面の不安が軽減
そのため前職よりも条件の合う会社に出会えました。
一方で、制度を知らなかった友人は貯金を切り崩し大変だったそうです。
つまり、知識の差が転職の安心感を大きく左右します。
まとめ:知識は最大の武器
転職には不安がつきもの。しかし社会保障を理解し、上手に活用すれば
そのリスクは大きく減らせます。
- 失業保険
- 国民健康保険・任意継続
- 国民年金免除制度
- 住民税・所得税の対策
- 職業訓練
これら5つは必ず押さえたい基本です。
私自身、制度を知っていたからこそ、
転職を「不安」から「成長のチャンス」に変えられました。
あなたもぜひ今のうちに制度をチェックし、
安心して次のキャリアに踏み出してください。
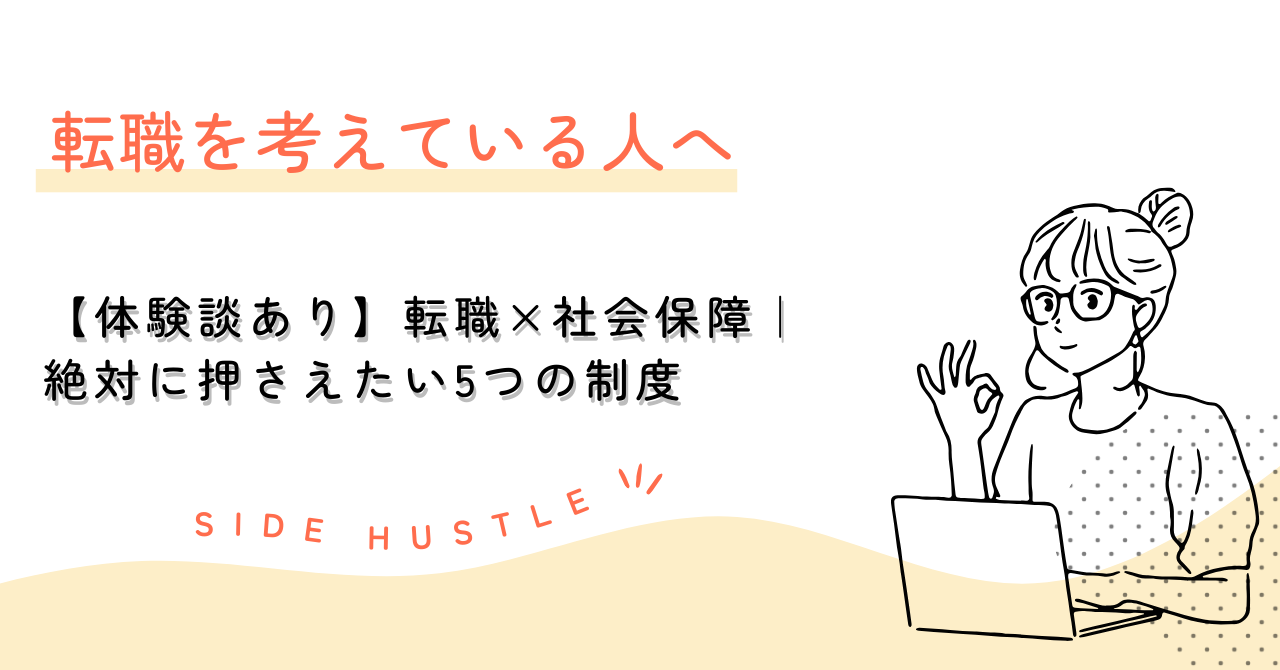

コメント